薬局長の仕事は人を育てること
薬局長としては主にどのような仕事をしていますか?
薬局長の仕事としては薬剤師のマネジメントというかキャリアプランの作成とサポートも仕事の一つです。例えば新人の薬剤師だったら、3年で一通り理解できるように到達目標をざっくりと決め、月毎に目標に沿った課題や仕事を振っています。この店舗には2年目と1年目の薬剤師が1人ずついます。他の薬剤師5人は、ほとんどがベテランの方なので一緒にサポートをしてもらいながら育てています。 私が新人の頃は半分泣かされるぐらいの怒られ方をして、とても辛かった記憶があります。新人の方にはそういう思いをしてほしくないので、自分はこう教わってきたとか、知っていることが前提で話をしないなど気を付けています。もちろんお客様にご迷惑をお掛けするわけにはいかないので、厳しくしなくてはいけないところはきちんと伝えていますが、できるだけ優しく伝えるよう心がけています。 他にはシフトの管理もしています。もちろん店舗の状況によるとは思いますが、最終的に薬局長が確認できれば良いものだと思うので、スキルアップも兼ねて他の人に任せていきたいと思っています。人に仕事を振るよりも自分でやった方が時間も労力もかからないという面や、仕事を振られた方は「面倒くさい」と思っている面もあると思いますが、その人が3年後に薬局長になった時のことを考えると、今のうちに経験しておく方が結果的に良いのではないかと思っています。
薬剤師として心がけていることはなんですか?
お客様をお待たせする時に混み具合を見ながらどのくらいの時間がかかるのか、具体的にお伝えするようにしています。「15分くらいかかります」と伝えておけば、お客様はドラッグストアでお買い物をしたりできますし、順番通りにお渡ししていることも伝わりやすくなります。内容によって順番が変わってしまう時は「次ですよ」とお声がけするようにもしています。
ウェルパークで実現した“イクメン”
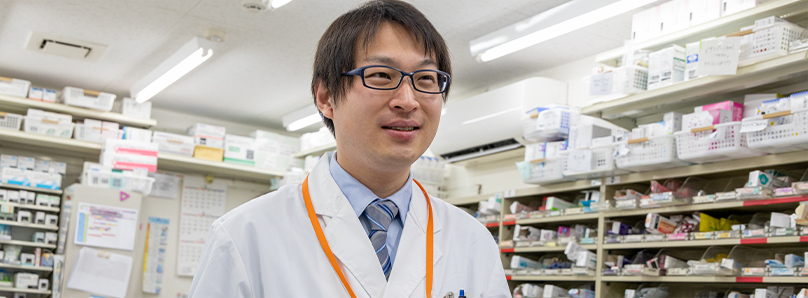
中途で入社されていますが、転職のきっかけはなんでしたか?
前職は新卒から調剤専門薬局に勤めていました。転職の理由は家族です。前の会社は9時から7時半のシフトでさらに3時間以上の残業がありました。在宅対応もしていたので、店舗を閉めた後9時頃に患者さんの家に薬を届けることもありました。やりたいことはとてもわかるのですが、子供もできたので環境を変えないとこの先10年、20年も続けることは難しいと思い転職を決断しました。
転職の際は調剤専門薬局とドラッグストアとで悩みましたが、前職で在宅のお客様のお話を伺った時に、おむつは重いから一緒に持ってきてほしいと言われるようなケースもありました。単独の調剤専門薬局では安く配達できないため、助けてあげたいのに助けてあげられないもどかしさがありました。でも店舗に在庫があり、かつ安い価格で売っているドラッグストアならばそういう形での手助けもできるのではと思いました。
なかでもウェルパークは、調剤メインでほぼ専従で、患者さんに直接調剤の時間を割けるということがメリットの一つでした。他のドラッグストアのように薬剤師も品出しやレジも担当してというのは、自分のやりたいものとは違うと感じていました。
ウェルパークでのお仕事はいかがですか?
前職で薬局長経験があったのでウェルパークでは薬局長の補佐的役割から始まり、会社の内規を勉強させていただいてから薬局長になりました。
先ほど子供が転職理由と言ったのですが、今は朝10時半出勤にさせていただいています。共働きなので、私が毎朝子供を保育園へ送って、奥さんは朝イチから働きその分時短で上がり子供を迎えに行っています。おかげさまで子供との時間も作れるし、奥さんの助けになるし、睡眠時間やプライベートの時間も充実しています。この様な環境で勤務できているのも、店舗にいるスタッフ、仲間たちの協力があるからこそだと思い本当に感謝しています。

40代、50代に向けて頑張っていきたいことはありますか?
ウェルパークが提唱する“生活サポート”は私が薬剤師になりたい思ったきっかけにとても近い理想でした。「どうやったらそこに近づけるのか」「どうやって実践していくのか」というのはとても難しいことですが、自分も一緒に作り出していきたいと思っています。
ヘルスケアサポートやセルフメディケーションと言ってこれからは薬局とお客様のつながりが求められていきます。体調が悪くても病院へ行っていいのわからないと悩むお客様がいらっしゃるのがドラッグストアだと思います。重症化する前の段階で改善できるものであれば、お薬でも栄養ドリンクでもサプリメントでも食材でも、お客様の生活に寄り添ったご相談に乗ることができますし、早めの受診も促すこともできます。しかし残念なことに、今はまだお客様に広く伝わっていないのが現状です。お客様にとっても薬局にとってもわかりやすく、使いやすいサポートの実現が今後の課題だと思っています。


 ご入社を検討されている方へ
ご入社を検討されている方へ