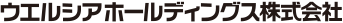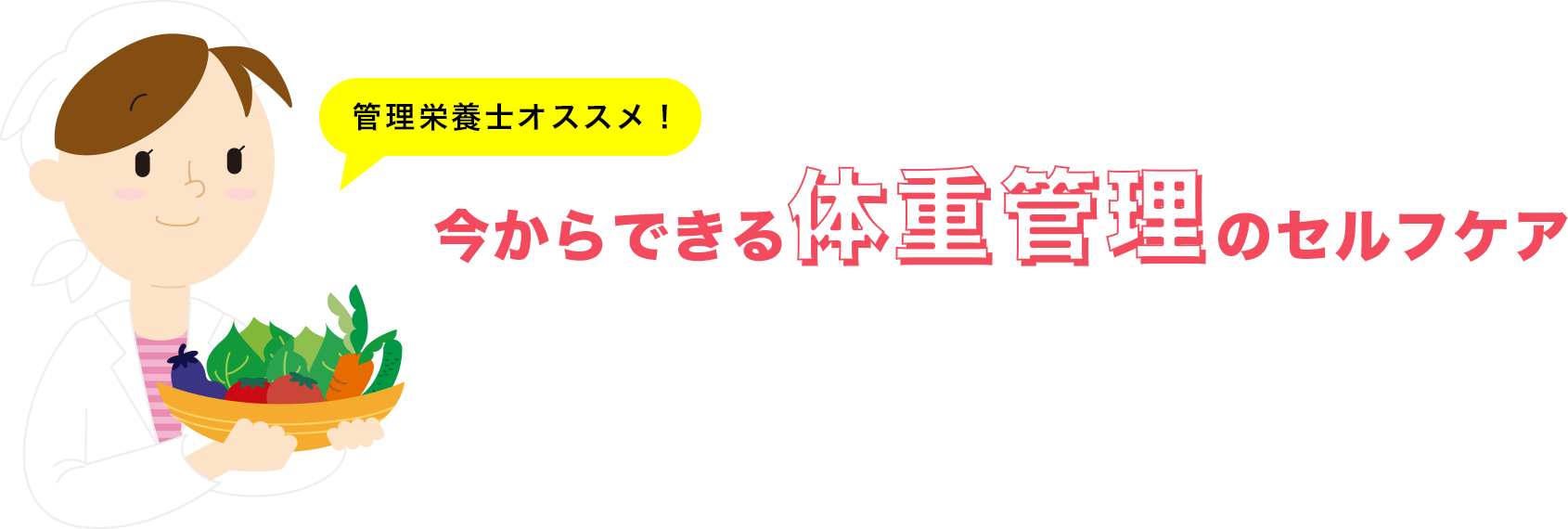【2019年10月】管理栄養士オススメ! 今からできる体重管理のセルフケア
カロリー・糖質・脂質など数多のダイエット。
制限しなきゃと思っていても、具体的にどうしたらいいかわからないですよね。
そこで、管理栄養士から見た、毎日の生活でできるちょっとしたポイントについてお話します!
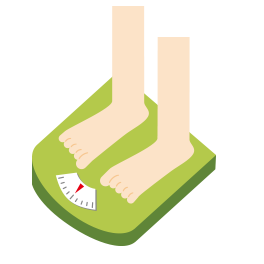 私、肥満なの?どれだけ食べたらカロリーオーバー?
私、肥満なの?どれだけ食べたらカロリーオーバー?
自分の体重はどのくらいなのか、どのくらいカロリーを取ってもいいのか知っていますか?最初に、基本的な「適正体重」と「推定エネルギー必要量」を調べてみましょう。
1「BMI」で肥満度check!
BMIとは、「Body Mass Index」の頭文字「B・M・I」をとったもので、体重と身長のバランスをチェックして肥満度を判定する国際的な基準なのです。日本肥満学会も、18.5以上25.0未満を普通体重として、それ以下を低体重・それ以上を肥満と定義しています。 そのため、健康保険被保険者が受ける「健康診断」でも、BMI25以上は「病気になる前に改善」を促す指導(特定保健指導)が入ります。
| BMI | |
| 低体重(やせ) | 18.5未満 |
|---|---|
| 通常体重 | 18.5以上〜25未満 |
| 肥満 | 25以上〜30未満 |
2カロリーcheck!
1日に必要なカロリー量を、推定エネルギー必要量といいます。下記の表は、デスクワーク中心のお仕事で、職場内での移動や立ち仕事、または通勤や家事、軽いスポーツを行っている場合の、日本人の平均的な体重を基にした推定エネルギー必要量です。自分の性別と年齢をもとに1日に必要なカロリー量を求めてみてください。
※推定エネルギーは年齢や性別、体重、日常の動作や運動量で異なります。アスリートや妊娠・授乳期の方等はこれには該当しませんのでご注意下さい。
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 18〜29歳 | 2,660kcal | 1,940kcal |
| 30〜49歳 | 2,680kcal | 2,010kcal |
| 50〜69歳 | 2,450kcal | 1,940kcal |
| 70歳以上 | 2,190kcal | 1,730kcal |
いかがでしたか?ご自分の目安が見つかりましたか?これらが一般的に言われる肥満度や1日に必要なカロリー量です。
過度な体重増加は、生活習慣病の原因にもなります。毎日や1週間に1度など、定期的に体重を知ることは日々の体調管理にもつながりますので、ぜひチャレンジしてみてください。
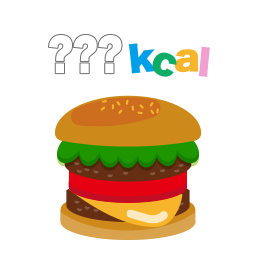 エネルギー??よく分からなくても大丈夫!
エネルギー??よく分からなくても大丈夫!
日々の生活で少しずつ改善できる!
ご飯は〇〇カロリー。ハンバーグは…。唐揚げは我慢して、やっぱり豆腐…??ひとつひとつのカロリーがわからなくても、日々の生活の中でも上手にコントロールできる方法をご紹介します。
1ゆっくり・たっぷり噛む
噛む回数が増えると満腹中枢が刺激されるので、いつもより量が少なくてもより満腹感が得られます。
2順番は、野菜→主菜→主食
野菜から食べると、食物繊維がお腹の中で膨れ、食べ過ぎ防止を防いでくれます。また、ごはんなど主食と比べると急激な血糖値の上昇を防いでくれるので、太りにくい体になります。
3食後すぐの睡眠、運動はNG!
食後は食事の消化をするために胃や腸が活発に働いています。なので睡眠や運動をしてしまうと内臓の動きが鈍くなり消化が遅れてしまうのです。食後1~2時間を目安に安静してみて下さい。
4朝ごはん必須!
実は、夜寝ている間にもエネルギーは消費されています。朝起きて頭が働かないのは、脳が飢餓状態となっているからです。一日の活動の準備をするためにも、朝食を欠かさず食べましょう。朝食を抜いてしまうと、体脂肪を溜め込みやすくなり肝臓でコレステロールが増加し、結果的に肥満につながってしまいます。
5深夜の食事はNG!
言うまでもないことですが、夜遅くに食事をすると脂肪を蓄えやすくなってしまいます。消化が遅れる→朝まで満腹が続く→結果、朝食を抜くことにつながり、まさに肥満の悪循環です。
6外食・コンビニ飯はチャンス!
レストランではメニュー表、コンビニではラベルなどにエネルギーや栄養成分が表示されています。日頃から見る習慣をつけると、どれくらいエネルギーを摂っているか知ることが出来ます。
7丼・コンビニ飯にはプラスワン
栄養バランスが偏り、野菜不足にもなりがちです。摂取カロリーも大事ですが、栄養バランスも大切です。サイドメニューでサラダや煮物をプラスしてみて下さい。
8主菜に迷ったら赤・青・皮なし
マグロの赤身や青魚、豚肉・牛肉ならひれ肉やもも肉、鶏肉ならササミやむね肉(皮なし)などの部位がオススメです。調理法は、刺身や焼く・煮る・蒸すなど、油を使わない方がより効果的です。
 おやつは、食べても良いのです!
おやつは、食べても良いのです!
ダイエットなどでは間食は大敵ですが、実は罪ではありません。選び方・食べ方を工夫してみましょう!一日の摂取カロリーを考える場合は、最初からおやつの分も確保しておくと、さらに安心して食べられますよ!
パンに注意!
菓子パンをおやつ代わりに食べる方はたくさんいらっしゃいますが、菓子パンは糖と脂質の塊。メロンパンはおよそ400kcalで、お茶碗山盛りごはん2杯分です。
清涼飲料水に注意!
ついぐびぐび飲みたくなってしまう清涼飲料水。500mlペットボトルでスティックシュガーおよそ19本分です。
“ながら食べ”にご注意!
テレビや携帯を見ながら、オフィスワークをしながらなど、無意識のうちにお菓子などをつまんでいませんか?“ながら食べ”は、噛む回数が少なく満腹感を感じにくくなってしまいます。結果、たくさんの量を知らないうちに食べてしまう原因となります。
おすすめはアーモンド
アーモンドやナッツ、無糖ヨーグルトなど、脂肪と糖質が少ないものを選ぶと、カロリーを抑えて普段の食事だけでは不足しがちな栄養素も摂取できるのでおすすめです。
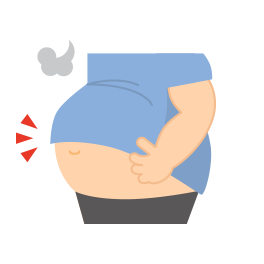 食べ過ぎちゃっても大丈夫
食べ過ぎちゃっても大丈夫
実は、食事のバランスは1日の中で足し引きできます。例えば、昼食を食べ過ぎてしまった日は、夕食をいつもより少なく野菜中心にするとバランスが良くなります。つまり、夜外食の予定があるときは朝食・昼食を軽くしておけば、一日の総摂取エネルギーを抑えることができるんです。
カロリーを上手にコントロールして、美味しく楽しく健康な日々を過ごしてみませんか。
参考文献:日本医師会
厚生労働省
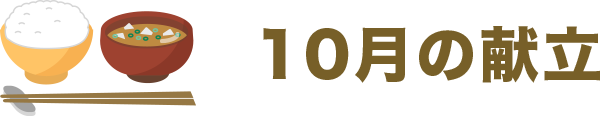

豚肉の冷しゃぶサラダ
- エネルギー
- 295 kcal
- 炭水化物
- 11.6 g
- タンパク質
- 26.7g
- 脂質
- 13.9 g
- 食塩
- 1.1 g
材料(1人前)
- ぶたもも 脂身つき
- 100g
- 酒
- 3g(小さじ2/3)
- サニーレタス
- 10g(葉1枚程度)
- キャベツ
- 15g(葉1枚程度)
- れんこん
- 20g(薄切り6切れ程度)
- にんじん
- 20g(薄切り6切れ程度)
- ヤングコーン
- 30g(4本程度)
*タレ*
- たまねぎ
- 10g(1/10個)
- こいくちしょうゆ
- 6g(小さじ1)
- ごま油
- 0.5g(少々)
- 本みりん
- 6g(小さじ1)
- ラー油
- 0.5g(少々)
作り方
1サニーレタスは手で食べやすい大きさにちぎり、キャベツは千切り、れんこんは半月切り、にんじんは短冊切り、たまねぎはみじん切りにそれぞれ切っておく。れんこんとたまねぎ、キャベツ・サニーレタスはそれぞれ水にさらしておく。
2レンコンとニンジンを一緒に芯が柔らかくなるまで茹でる。茹で終わったら、ざるに上げ、冷ます。
3沸騰した鍋に酒を入れ、豚肉をさっと茹でたら、氷水に通して水を切る。
4ヤングコーンはフライパンで焦げ目がつくまで炙り、水を入れて蓋をしたら火が通るまで蒸す。
5皿に水を切ったレタス・キャベツをひき、豚肉、れんこん、ニンジン、ヤングコーンをそれぞれ盛り付ける。あらかじめ混ぜておいたタレを上からまんべんなくかけたら完成。
POINT
- 豚肉は茹でたあと氷水に通すことで、さらに油を落とすことが出来る。
- タレにたまねぎを入れることで塩分を調節する。
- 肉以外にも歯ごたえのあるレンコン、にんじん、ヤングコーンがあるため、食べごたえがある。
- 野菜盛りだくさん!

れんこんエノキの入ったピーマンの肉詰め
- エネルギー
- 326kcal
- 炭水化物
- 14.5 g
- たんぱく質
- 18.0 g
- 脂質
- 19.1 g
- 食塩
- 1.1g
材料(1人前)
- ピーマン
- 120g 2個
- 鶏ひき肉
- 80g
- れんこん
- 20g (薄切り4切れ程度)
- えのきたけ
- 10g
- 食塩
- 0.1g 少々
- 薄力粉
- 0.1g 少々
- サラダ油
- 12g 大さじ1
- 水溶き片栗粉
- 0.5g 少々
*タレ*
- こいくちしょうゆ
- 6g 小さじ1
- 本みりん
- 6g 小さじ1
- 上白糖
- 1g 少々
作り方
1ピーマンをたて半分切り種をとり、れんこんはさいの目切り、えのきは石づきをとりみじん切りにする。れんこんは水にさらしておく。
2ボールに鶏ひき肉・食塩を入れ軽く手で捏ね、れんこん、えのきを加えて更に捏ねる。
3捏ね終わったタネを冷蔵庫で15分くらい置き、なじませる。
4ピーマンの内側に小麦粉をまぶし、冷蔵庫から出したタネを詰める。
5中火にしたフライパンにサラダ油をひき、肉を下にしてピーマンを焼く。
6あらかじめ混ぜておいたタレをフライパンに加え、ふたをする。
7火が通ったら、ピーマンを裏返し、水溶き片栗粉を加えとろみをつけたら完成。
POINT
- エネルギーの低い鶏ひき肉を使用した。
- れんこんとえのきを加えることで、かさましをした。
- 食物繊維の多いれんこんを使用することで、少しのお肉でも満腹感が得られるようにした。